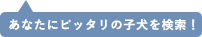ミニチュアピンシャーは家族への忠誠心が非常に強く、警戒心も強い事から、
番犬に最適な犬種といえます。

吠え方も、他の小型犬とは全く異なって本格的です。
プライドが高く、神経質な面があるため、
小さなお子様のいる家庭にはあまり向かない犬種です。
乱暴な扱いをされると、攻撃的になって噛み付くこともあるからです。
もともと無駄吠えが多い方で、早いうちから
しっかりとしたしつけが必要です。
また、MPCA(アメリカのミニチュアピンシャー公認団体)では、
「
Escape Artists(脱走の芸術家)」と紹介されています。
興味のあるものへの探求心が強く、そのためにはどんな事をしてでも
脱走を試みると言われていますので、ワンちゃんが迷子にならないよう
子犬のうちからしつけるようにしていきましょう。
また、人が大好きで甘えん坊、寂しがり屋な面もありますので、
十分なコミュニケーションをとるようにしましょう。
ミニチュアピンシャーはきれい好きで、飼育環境を汚さない事でも有名な犬種です。
小柄ながらエネルギッシュなので、毎日の運動に付き合える人にお勧めです。
また、ミニチュアピンシャーは夏の暑さや冬の寒さが苦手です。
暑さが厳しい時期は直射日光が当たるところでの散歩はなるべくひかえましょう。
寒さが厳しい時期は暖かい犬用セーターなどを着せたり、
ペットヒーターを入れるなど防寒対策をしてあげましょう。
1. ブラッシング
ミニチュアピンシャーは短毛ですが、見た目以上に毛量が多いため、抜け毛は多い方です。
そのため、しっかりとしたブラッシングが必要です。
・換毛期の死毛除去には、ラバーブラシがお勧めです。
・散歩後には、ノミ取りコームでブラッシングしてあげましょう。
・毛艶を出すためにも、ブラッシングの仕上げには獣毛ブラシがおすすめです。
2. 耳のお手入れ
ミニチュアピンシャーの中でもとくに垂れ耳の場合は、手入れ不足によって外耳炎などを
引き起こしますので、適度にお手入れしてあげましょう。
もし、耳垢が黒い(健康な時は薄い茶褐色)、異臭がするなどといった異常を見つけたら、
早急に獣医師の診察を受けましょう。
・生後2ヶ月頃から徐々に慣れさせましょう。
・余分な毛はカットして、通気性を良くします。
・綿棒にイヤーローションなどをつけて、頭をしっかり押さえて優しく拭き取ります。
・耳内部の皮膚は大変デリケートですので、あまり力を入れすぎないように注意しましょう。
刺激によって炎症を起こす事があります。
・シャンプー後も、耳内部の水気をガーゼなどで優しく拭き取ってあげましょう。
3. 爪切り
爪切りは少々難しいお手入れの一つですが、衛生面を考えても必要なお手入れです。
爪切りを怠ると、元々爪の中にある神経や血管が先端の方にまで伸びてきてしまい、
いざ爪きりするときに出血を伴うようになってしまいます。
そうなる前に、定期的に爪きりを行うようにしてください。
・生後3週間ほどから、しつけの一貫として、徐々に慣れさせましょう。
・シャンプー後は多少切りやすくなるのでおすすめです。
・肉球の先端部分より延びた部分がカットする目安です。
・深く切り過ぎないようにしましょう。
・万が一切りすぎた場合は、止血剤をしっかり塗布してあげます。
・心配な方は、プロに任せても良いでしょう。
4. シャンプー・トリミング
あまり頻繁にシャンプーをすると体毛の油分が抜けてしまい、光沢が鈍くなったり、
体毛の乾きが遅くなったりするので月に一度で十分でしょう。
気になる時は蒸しタオルで拭いてあげると、
マッサージにもなり、毛艶も出てよいでしょう。
◎レッグペルテス病
(症状)
レッグペルテス病は大腿骨頭にある血管が傷ついて血液の供給量が不足し、骨頭が壊死することによって
起こる病気です。
後ろ足の血管の働きに異常が起き、突然足を痛がる、歩くときに足を引きずるなどの症状が現れます。
片足だけに起こることがほとんどです。
小型犬に多く、1歳以下の成長期の子犬に起こります。
(対策)
レッグペルテス病は発症する原因が分からないため、予防はできません。
レッグペルテス病は放置して治る病気でなく、股関節の関節炎を一生持ち続けることに
なってしまいますので、できるだけ早く手術を受ける方がよいです。
手術が遅れると術後のリハビリに時間がかかってしまいます。
特にこの病気が多く見られる犬種で上記の症状が見られたら、
放置せずにすぐに動物病院へ連れていきましょう。
◎膝蓋骨脱臼
(症状)
膝蓋骨脱臼は、後足の膝関節にある膝蓋骨(お皿) がはずれてしまう病気です。
膝蓋骨脱臼が起こると、足を痛がって引きずるようになったり、
脱臼した足を浮かせるようにして歩くなどの症状が現れます。
膝蓋骨が内側にずれる内方脱臼と、外側にずれる外方脱臼があり、
一般的に症状によって4段階に分けられます。
その中でも症状が脱臼よりも比較的軽い亜脱臼は、小型犬でよく見られます。
膝蓋骨脱臼の原因としては、先天性と外傷などの後天的なものがあります。
先天的な原因としては、膝関節のまわりの筋肉や骨、靭帯の形成異常などがあり、
年齢とともにこれらの異常が進行することで発症します。
後天的なものとしては、打撲などの外傷や高いところからの落下による骨の変形などが原因になります。
(対策)
膝蓋骨脱臼を予防するに方法は、膝に負担をかけないことです。
子犬の時から、いすやソファに飛び乗ったり飛び降りたりする習慣をつけないようにしましょう。
また、フローリングなど硬くてすべりやすい床は膝へ負担かかるので、
じゅうたんやマットなどを敷くと良いでしょう。
 ミニチュアピンシャー飼育上の注意点【 ミニチュアピンシャー・ブリーダーズ 】
ミニチュアピンシャー飼育上の注意点【 ミニチュアピンシャー・ブリーダーズ 】 ミニチュアピンシャー飼育上の注意点【 ミニチュアピンシャー・ブリーダーズ 】
ミニチュアピンシャー飼育上の注意点【 ミニチュアピンシャー・ブリーダーズ 】